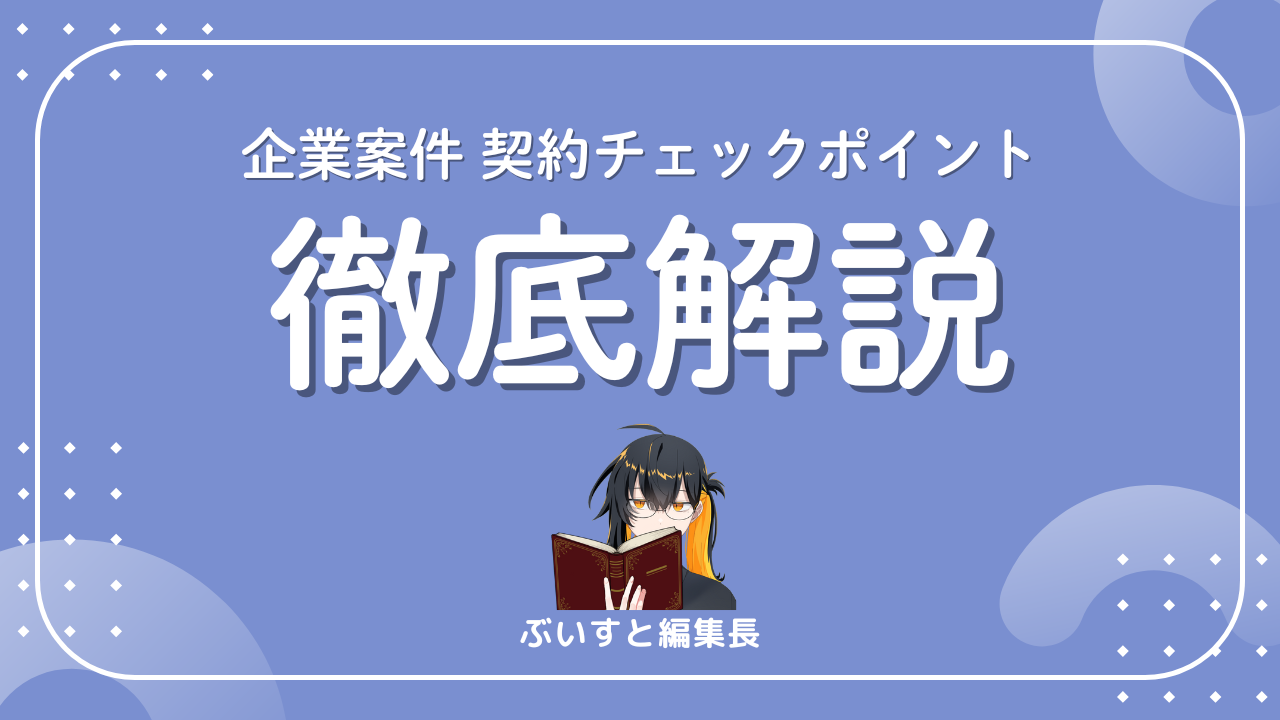はじめに:その契約、ちゃんと読んでいますか?
「企業から案件の話が来たけど、契約書ってどう読めばいいの?」「うっかり不利な条件で契約してしまわないか不安…」
そんな悩みを持つ配信者さんは少なくありません。
この記事では、「企業案件 契約チェックポイント」という観点から、配信者が契約前に絶対に確認しておきたい項目を、具体例を交えて解説します。
報酬:額面・支払い時期・条件のすべてを明確に
企業案件でもっともトラブルになりやすいのが、報酬の支払い条件です。
報酬額はもちろん、「いつ、どうやって支払われるのか」「条件付きかどうか」などが契約書にどう書かれているかを、必ず確認しましょう。
条文例
第4条(報酬および支払い方法)
甲は乙に対し、本件業務の報酬として、金5万円(税込)を支払う。
支払いは、納品完了後30日以内に、乙が指定する銀行口座へ振込送金する方法によって行う。
チェックポイント
- 金額が明記されているか?
→ 曖昧な記述(「別途協議」など)は要注意。 - 税込 or 税抜が明確か?
→ 消費税が含まれているか否かで実際の入金額が変わります。 - 支払い時期が明記されているか?
→「納品後30日以内」などの文言を見逃さず、後日揉めないように。 - 振込手数料の負担者は誰か?
→ 書かれていない場合、実質的な報酬額が減る可能性も。
補足:成果報酬型・再生数連動型にも注意
一部の企業案件では、「◯◯再生以上で追加報酬」「クリック数に応じて報酬変動」など、成果連動型の契約が増えています。
この場合も、
- 何を成果とみなすのか(再生数、クリック、エンゲージメントなど)
- 測定方法は誰がどう判断するか
- 最低保証報酬はあるか
といった観点を、事前にチェックしておくことが重要です。
このように、報酬に関する条文は「もらえるお金の話」ではなく、「ちゃんともらえるかどうかの話」です。
契約書は、“約束の証拠”です。あとから言った言わないにならないよう、報酬の条件は必ず書面で確認し、疑問があれば事前に確認しましょう。
権利:誰が使えて、どこまで使われるかを確認する
企業案件において、「制作物の権利」や「出演内容の利用範囲」は見落とされがちですが、非常に重要です。
たとえば、コラボ配信で使ったキャラクターイラストが、事前の合意なく販促物に使われていた…。
そんな事態を防ぐためには、「権利の帰属」と「使用範囲」を明確にしておく必要があります。
条文例
第7条(成果物の権利)
本件業務の遂行により生じた成果物(音声、映像、画像等)の著作権その他一切の権利は乙に帰属するものとする。ただし、甲は自己の広報・宣伝活動において、乙の事前承諾を得たうえで成果物を利用することができる。
チェックポイント
- 権利の“帰属先”がどちらかを確認
→ 通常、出演者が権利を持つ場合と、企業が「買取り」する場合があります。 - 使用の許諾範囲が明記されているか?
→ SNS投稿、CM素材、イベント投影など、利用される場面は事前に想定しておきましょう。 - 再利用・二次利用が可能かどうか
→ 今後、関係ない案件で使いまわされるリスクを避けるためにも、制限をかけておくのがベターです。
補足:肖像権・声の利用も「権利」の一部
配信者として出演した映像や音声も、契約上は「成果物」や「コンテンツ」として扱われることがあります。
とくに、AI音声の合成や切り抜き動画の二次利用などが含まれる場合は、「どこまで使ってよいか」「どれくらいの期間使うのか」まで細かく確認しておく必要があります。
「一度出演したから、あとは企業が自由に使っていい」わけではありません。
契約における「権利」とは、あなた自身のイメージや作品を守るためのラインです。気になる点があれば、必ず事前にすり合わせておきましょう。
秘密保持:お互いの信頼を守るための前提条件
企業案件では、案件の詳細や製品情報が正式発表前に知らされることがあります。
また、配信者側も、まだ公開していない活動計画や裏側の体制など、企業に共有する場面があるでしょう。
こうした情報の取り扱いについて定めるのが、「秘密保持条項」です。トラブルを防ぐための基本的な取り決めとして、必ず目を通す必要があります。
条文例
第9条(秘密保持)
甲および乙は、業務遂行上知り得た相手方の技術上、営業上その他一切の非公開情報を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に漏洩してはならない。
本条の義務は、本契約終了後も3年間継続するものとする。
チェックポイント
- 「秘密情報」の範囲が定義されているか?
→ メール、企画書、会話の内容などが含まれるかどうかを確認。 - 第三者への開示条件が明示されているか?
→ 所属事務所やマネージャーとの共有が必要な場合は、その点を明確にしておく。 - 契約終了後も義務が続くか?
→「契約終了後◯年間有効」といった記載に注意。情報の取り扱いは長期にわたる場合があります。
補足:うっかりSNSで漏らさないために
配信者にとって、日常の発信は生活の一部。
しかし、リリース前の商品情報や未発表のコラボ内容をうっかり話してしまうと、大きな信用問題に発展します。
「どこまで話してよいか」「どこからがNGか」は、契約書の記述と担当者の説明をあわせて確認するのが安心です。
秘密保持条項は、企業側を守るだけでなく、自分自身の立場や信用を守るためにも重要です。
書かれている内容をよく理解し、不安な点は遠慮なく質問しましょう。
解除:案件が途中で終わるとき、どうなるのか
どんなに良好な関係で始まった案件でも、途中で終了する可能性は常にあります。
たとえば、企業側の予算都合、炎上リスク、配信者の体調不良など、想定外の事情で「案件中止」が発生することも。
そんなときに揉めないようにするために、契約書には「解除」に関する条項が設けられています。
「どういう条件で契約を終了できるのか」「終了時に報酬はどうなるのか」を確認しておきましょう。
条文例
第10条(契約の解除)
甲および乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず是正されない場合、本契約を解除することができる。
また、やむを得ない事情により業務継続が困難となった場合は、相手方に書面にて通知し、合意のうえで解除することができる。
チェックポイント
- 解除の条件が具体的に書かれているか?
一方的な都合での解除が許されているかどうかに注目。 - 報酬の扱いが明示されているか?
途中まで進めた業務に対して「日割り報酬」や「実費精算」があるか、確認が必要です。 - 通知期間(何日前までに連絡が必要か)があるか?
「解除は○日前に通知すること」などの規定がある場合、スケジュールへの影響も考慮する必要があります。
補足:炎上時の「対応方針」も要チェック
昨今では、SNS上の炎上や誤解が原因で急遽案件が白紙になるケースも見られます。
契約解除条項には、「イメージ毀損時の対応」や「反社会的勢力との関係が発覚した場合の解除」など、細かいリスク回避条件が盛り込まれていることもあります。
配信者側としても、「何が理由で契約が打ち切られるのか」「そのときに報酬は支払われるのか」を、冷静に確認しておくことが重要です。
「解除条項」は、できれば使いたくない条項です。
でも、いざというときに泣き寝入りしないための保険でもあります。契約の締結時にこそ、丁寧にチェックしておきましょう。
禁止事項:知らずに違反しないための「地雷チェック」
契約書には多くの場合、「やってはいけないこと=禁止事項」が明記されています。
これらは、企業の信用を守るため、また配信者側の行動を制限するために設けられています。
でも中には、「こんなことまでNGなの?」という内容が含まれていることも。
知らずに違反してしまえば、契約の解除や損害賠償につながる可能性もあります。
条文例
第11条(禁止事項)
乙は以下の行為を行ってはならない。
(1)甲または第三者の名誉・信用を毀損する行為
(2)甲から提供された資料・情報の無断転載・転用
(3)甲との本件契約と競合する行為
(4)業務遂行上知り得た情報の漏洩
(5)その他、甲が不適切と判断する行為
チェックポイント
- 競合案件の受託制限があるか?
→ 他社の類似製品やサービスを同時に紹介することを禁止する条項が含まれている場合があります。 - 発言・SNS投稿の内容に制約があるか?
→ 案件に関係のない配信やSNSでの発言でも、契約違反になることがあります(例:「甲に不利な投稿を禁ずる」等)。 - 「その他不適切な行為」といったあいまいな表現
→ 運用次第で広く解釈されることがあるため、できるだけ具体的な定義や例示を確認しましょう。
補足:「知らなかった」は通用しない
禁止事項に関しては、「知っていたかどうか」ではなく、契約で「同意したかどうか」がすべてです。
つまり、一度サインしてしまえば、たとえ細かい条項まで目を通していなくても、違反すれば責任を問われる可能性があります。
特に、普段の配信スタイルや言動が契約先企業とマッチしないケースでは、思わぬ形で“地雷”を踏んでしまうことも。
契約書の「禁止事項」は、活動の自由度に影響を与える重要なパートです。
内容に違和感がある場合は、事前に相談・交渉することを恐れないでください。
自分らしい活動を守るためにも、「どこまでがOKで、どこからがNGか」を確認しておきましょう。
最後に:契約は「活動を守るための道具」です
契約書を読むことは、少し難しそうに感じるかもしれません。
でも実際は、「自分がどんな約束をしていて、どんな責任や権利があるのか」を知るための、大切なステップです。
本記事では、配信者の方が企業案件に臨む際に押さえておきたい「報酬」「権利」「秘密保持」「解除」「禁止事項」の5つの項目を取り上げました。
少しでも理解の助けになれば幸いです。
なお、契約書の読み合わせや、「この内容は不利なのか?」といった個別具体的なご相談については、「ひとこま依頼箱」で対応を受け付けています。
必要に応じて、お気軽にご利用ください。
ひとこま依頼箱
※当サイトおよび「ひとこま依頼箱」は、いずれも弁護士による法律相談サービスではありません。
内容はあくまで実務・経験に基づくアドバイスであり、最終的な判断には専門家の意見をあわせてご参照ください。